 |
 |
 |
||
| ↑すくも 藍の染料であるすくもを拡大していったら、インジゴの分子が見えてくるという概念的な説明の為の図 |
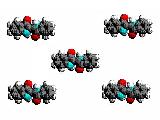 |
 |
|
◆なぜ化学?
◆染色という現象や薬品を化学の目で
藍の染料のミクロの世界を覗いてみよう。 日本における藍の染料は、すくもと呼ばれている。この土のようなすくもには、インジゴという青い色素が含まれている。顕微鏡で拡大しても決して目で見ることのできない小さな世界であるが、「ミクロの世界を覗く」というイメージは、次のようである。
|
 |
 |
 |
||
| ↑すくも 藍の染料であるすくもを拡大していったら、インジゴの分子が見えてくるという概念的な説明の為の図 |
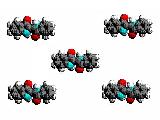 |
 |
|
こういった分子の性質やその振る舞いを、分子1粒1粒の立場に立って考えるのが化学である。
染色も、分子というミクロのレベルで考える必要がある。なお、分子というのは、極めて小さなツブである。 ◆染色とはどういう現象なのか
染料の分子と、繊維の分子がくっつく(親和性がある)とは、主に、分子の持つ電気的なプラスとマイナスの吸引力や、分子同士の引力に基づく力である。このような親和性があるかないかで、同じ染料で同じ条件で染めても、繊維の種類によって、染まったり、染まらなかったり、濃く染まったり、薄く染まったりする。 たとえば、マイナスの電気を帯びた染料の分子を考えてみよう。マイナスの電気を帯びていると言うことは、この分子に水溶性という性質も与えており、水に溶解する。繊維の分子にプラスの電気を帯びた部分があれば、この染料のマイナスの部分と引き合い、結合が生じ、いくら水で洗っても、染料の分子が繊維から離れることはない。羊毛・絹・ナイロンの分子にはプラスがあるので、この染料の分子と結合する。このような結合は、「イオン結合」と呼ばれる。 |
 |
 |
| オレンジIIという染料の水溶液に、羊毛・絹・木綿・ナイロン・アクリルの5種類の布をしばらく浸す。染料水溶液が布にしみ込んでおり、どの布もオレンジ色に染まったかに見えるが、よく水洗いすると、、、。 | 染色結果:左から、羊毛・絹・木綿・ナイロン・アクリル。羊毛・絹・ナイロンやよく染まった。木綿は、うっすらと色がついただけ。アクリルは全く染まっていない。 |
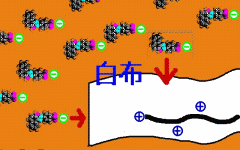 |
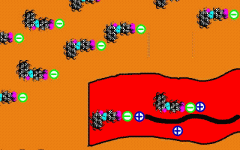 |
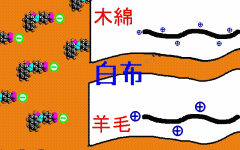 |
| 今回の染料は、オレンジIIという名前で、その分子は、マイナスの電気を帯びている(陰イオンである)。図には、分子一粒一粒が、水の中に散らばっている様子を示した。 染料液に布を入れると、染料水溶液は繊維の中にしみ込み、染料分子は繊維の分子と繊維の分子の間に入っていく。図では、布の中にある繊維の分子の1本を黒い線で示した。 |
繊維の分子にプラスの電気を帯びた部分があると、マイナスの電気を帯びた染料の分子は、プラスとマイナスの結合、即ちイオン結合で結合する。このような結合が起こるので、染料の分子は水溶性であるにもかかわらず、洗っても繊維から流れ出ない。つまり染色された、染着した、ということになる。 | 羊毛や絹やナイロンの繊維の分子には、プラスの電気を帯びた部分があるので、左の図のように、マイナスの電気を帯びた染料の分子と結合できるが、木綿の分子は、プラスの電気を帯びた部分はあるものの、弱い(上図では、小さな+で表現)ので、染料の分子を引き止めておくことができず、洗うことで染料が流れ出てしまう。アクリルの繊維の分子は、プラスを帯びた部分が無いので、染料分子を結合させることができない。 |
|
染料分子と繊維の分子との結合は、上のようなイオン結合による以外に、水素結合(イオン結合よりも弱いプラスとマイナス間の引き合いによるもの)や、分子間力や、配位結合によるものがある。また、染料分子と繊維分子を化学的に反応させ、共有結合を形成させることで結合させるタイプの、反応染料という染料もある。 ◆染色には危険な薬品も使われている
|
|
◆草木染めで劇物を使うことについて
|