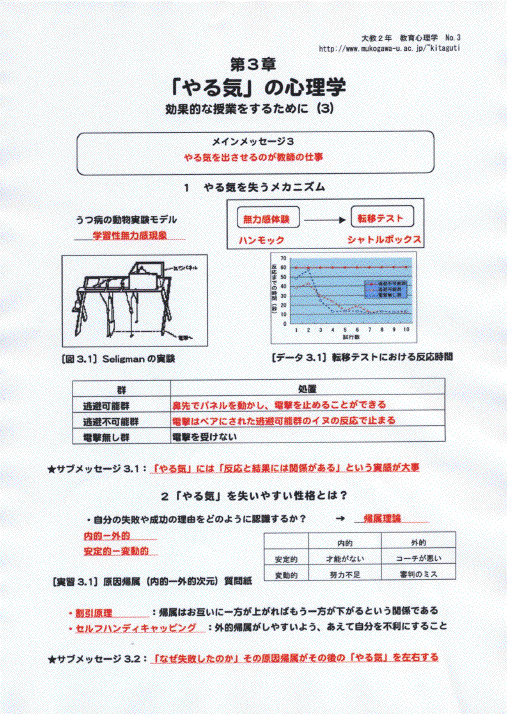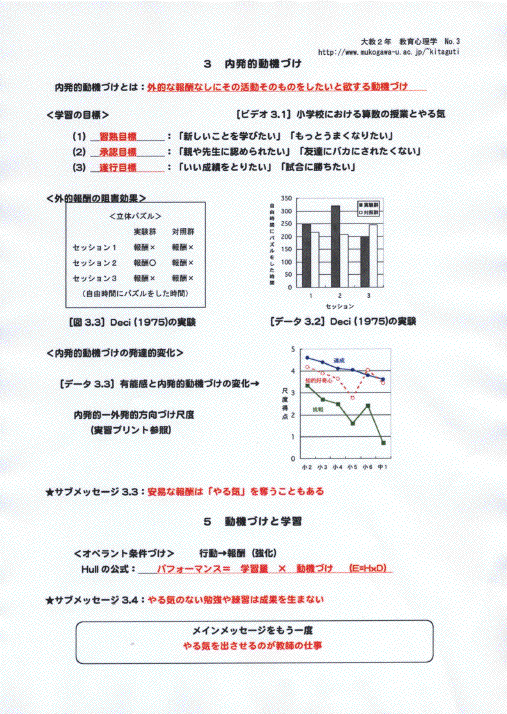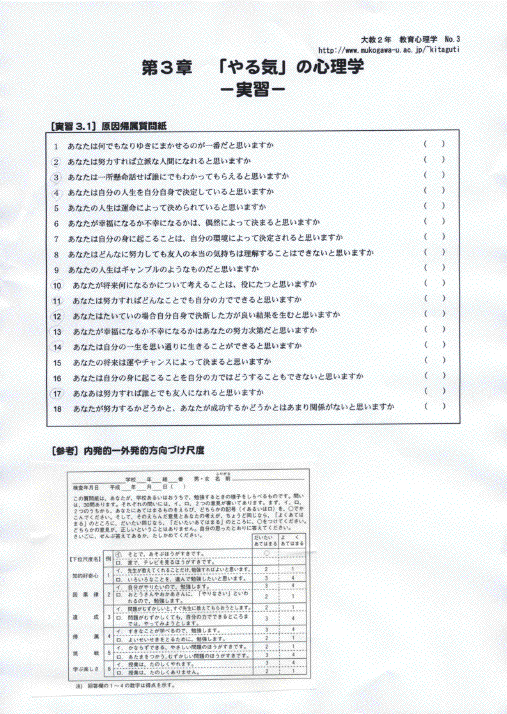第4章 「やる気」の心理学
効果的な授業をするために (3)
講義で使ったpptファイルです
| Slides |
質問はこちらへ!
もっと詳しく知りたい人へ
| Books |
|
やさしい教育心理学 鎌原雅彦・竹綱誠一郎 |
有斐閣アルマ 1999 \1900 |
|
学習意欲の心理学 桜井茂男 |
誠信書房 1997 \1800 |
|
学習性無力感 ピーターソン・マイヤー・セリグマン |
二瓶社 2000 \5200 |
関連HPはこちら
| Link |
|
|
|
|
予習
今までの学校生活の中で、評価(テスト、学期末の通知簿など)についての思い出を語ってください。別に面白い話でなくても、その時に自分がどう思ったとかでけっこうです。
以上の質問にメールで答えてください。
(クラス、番号、氏名を忘れずに!)
| →kitaguti@mwu.mukogawa-u.ac.jp |
| Top |