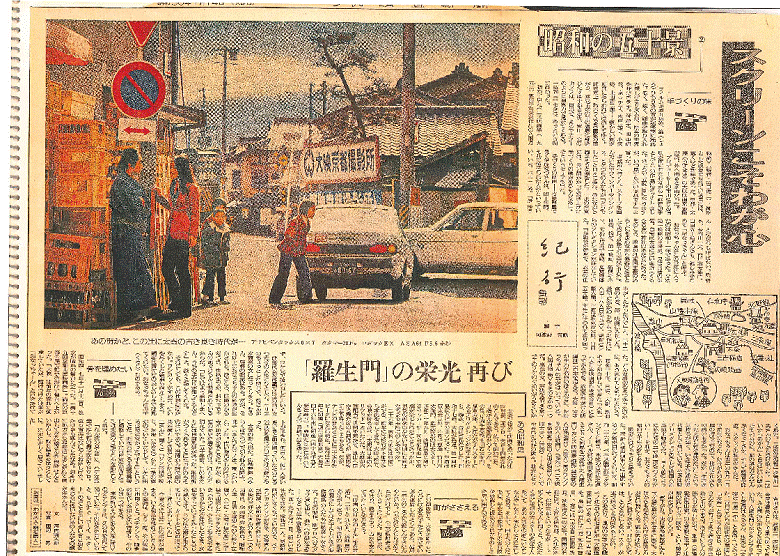第22話 「京都太秦物語」(2012年3月)
立命館大の図書館。出会いが生まれる。派遣としてカウンターで働く京子と、客員研究員の榎大地が甲骨文字の本を巡って、ぎこちない会話を始める。このシーンには既視感がある。そうだ。第2話『ある愛の詩』も、出会いはこんな風だった。彼は大富豪の息子、カウンターに座る彼女はイタリア移民のピザ屋の娘。こちらの彼女は太秦の大映通り商店街にあるクリーニング店の娘、彼はあの白川静博士を敬愛する若き研究者。いつも意外な結びつきに図書館が役目を果たす。図書館が、なぜ出会いに必要なのかと思いながら、映像を見つめる。
舞台の太秦。記者時代になんども取材で通った大映通り。昭和28年の『雨月物語』に携わった人々を追いかけたことがある。 幽玄の世界を創造した溝口健二監督の名作だ。お願いして試写室で、この映画を一人で見せてもらった。琵琶湖を漂う小舟のシーンや若狭の朽木屋敷の深い霧の場面はいまでも残っている。ゆかりの人たちが健在だった戦後30年の企画連載の取材(※)。通りには侍や町娘役の俳優たちが、衣装のまま普通に歩いていた。町全体に映画全盛期の思い出がしみ込んでいた。うどん屋に入ると、おばちゃんが常連だった大スターの名をたちまちに何人もあげてくれた。
『京都太秦物語』にも、クリーニング、豆腐、一膳めし屋、電器屋、本屋など、小さな店を切り盛りする人々が登場する。実在のオッチャンやおばちゃんたちが現れて、若いころの楽しかった時代や苦労話を語る。ドキュメンタリー作品のように、それが次々と挿入されながら恋物語は進行する。愉しい手法である。実在の人物が達者で、話す言葉がいい。
研究一筋という「榎」は行動も少々変わっている。返却する書籍に、みずから作った漢詩を添える。それが彼の恋文だ。思い立ったら、クリーニング店にも上がりこみ、屋根の上の物干し場まで登ってゆく。図書館の書庫にも入り込んで語りかける。困惑しながらも、京子はひたむきさに惹かれ、彼の研究発表を聞きにゆく。だが、彼女には幼馴染の豆腐屋の息子、梁瀬康太という恋人がいる。お笑い芸人を目指しているが、独り立ちできそうにもない。出身大学でもある立命館の大学祭で、芸を披露するが、誰も残ってくれない。
物語は、その三人の純粋な気持ちの揺れ動きを映画の街の人々、古都の四季の風景を織り込んで進んでゆく。
大学図書館、司書、研究者、白川学、学生、キャンパス。その素材はいつの間にか、消えてゆく。京都を離れ、東京に戻る「榎」。新幹線のチケットは京子に渡してある。発車の時刻。現れない。在来線のホームに立つ京子。鳴りつづける携帯電話をとるが声を出せない。見上げると列車はもう動き出している。そして、京子は少し涙をこぼしながら嵐電で戻り、太秦に生まれ育った康太を選ぶ。ラブストーリーである。
『京都太秦物語』を見て、ふと考える。図書館は「出会いの場」だけなのだろうか。出会いのその先にあるものにまで、映像はたどり着いてくれない。多くの映画に図書館も、そこで働く人々も登場はする。でも決して主人公にはならない。きっといいドラマが生み出せるのにと思う。これほど、自由な空間はない。これほど想像力を育むスペースは見つからない。活字で生きてきた人生だが、一度、映像と関わってみたい。そのときのメインキャストは図書館である。
![]()
『京都太秦物語』は立命館大学に映像学部が新設されたことにちなんで、松竹と立命館によって共同制作された。公開は2010年5月、客員教授でもある山田洋次さんと、阿部勉さんが監督をつとめた。出演は京子に海老瀬はな、榎大地に田中壮太郎、梁瀬康太にUSA(EXILE)ら。