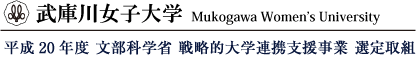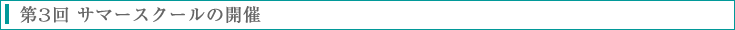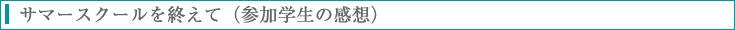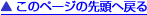平成23年8月29日、30日に第3回サマースクールを開催し、5大学の学生、大学院生、教職員ら60名が参加しました。1日目の中村ブレイス株式会社 中村社長の特別講演=写真=では、新しいことに挑戦する精神、一人ひとりのニーズに応える重要性、自信を持って行動することの大切さを学びました。また、竹製の義足や人工乳房などを実際に学生が手に取り、どのような発想で製品開発に取り組んだのか、お聞きすることができました。

中村 俊郎 社長

コミュニケーション講座
午後には「実践コミュニケーション講座」=写真=にて、参加者間のコミュニケーションを図るとともに、この後に行われるグループワークの進め方についてレクチャーを受けました。
サマースクールのメインとなるグループワーク=写真=では、「10年後の日本の社会を想定し、新しい医療・福祉サービスを提案する」というテーマのもと、各グループが与えられたキーワード(少子・高齢化、女性の役割・視点、地域活性化、社会貢献、医療・福祉の国際化、人材育成)をベースに活発な議論を展開し、2日目のグループワーク発表会に向けて、夜遅くまで資料を作成しました。
また、1日目の夜には懇親会が開催され、グループワークとは違ったリラックスした雰囲気で学生同士が交流したり、ゲーム大会で盛り上がりました。
2日目のグループワーク発表会=写真=では、司会進行・質疑応答もTAの大学院生や学生が担当し、発表内容も含めて相互に採点し、上位3グループまでが表彰されました。

グループワーク風景

グループワーク発表会
第1位 Dグループ
中村政文、山田竜介(関西大学)、櫻井祐太(大阪薬科大学)、篠原千奈、稲垣恵理、由良知彩(武庫川女子大学)
タイトル(キーワード):地域活性化、医療・福祉における新規産業(地域活性化、社会貢献)
第2位 Eグループ
根路銘良介、山本 翔平(関西大学)、小野敬洋(大阪薬科大学)、町田耕一(大阪大学)、奥本美佳(武庫川女子大学)
タイトル(キーワード):これからの医療(医療の国際化、人材育成)
第3位 Aグループ
市川智紀、山口浩正(関西大学)、市川理那、番匠志保(武庫川女子大)
タイトル(キーワード):保育施設と老人ホームを合わせた総合福祉施設の提案(少子・高齢化、女性の役割・視点)
生活環境学部 食物栄養学科
2年 玉城 真希
この2日間、とても貴重な体験ができました。そして参加者の皆さんや講演のお話からとてもいい刺激をいただきました。私達のグループは、少子高齢化に焦点をあててグループワークをしました。1つの問題に対して、薬・福祉・機械・食などあらゆる分野から見た考えや意見、知識などをシェアすることはとても面白く、こんな考え方・見方、発想があるんだなと、とても感動しました。普段の生活だと知り会えない、いろんな考え、性格をもつ皆さんと交流できてとても充実した2日間を過ごすことができました。
また、グループで1つのものを作り上げていくのは大変でした。いろんな意見が出る中で方向性を見失うことも多々あり、うまく話が進まないこともありました。しかし、失敗も反省点も含めて、今後に活かせる意味ある時間が過ごせたと思います。また、グループワーク以外でも会場ではいろんな先輩や先生から貴重なお話が聞ける機会があってよかったです。グループのために的確なアドバイスを投げかけてくださったTAの方々や、話し合いにヒントや指摘をくださったスタッフの先生にも大変感謝しています。
このサマースクールを通して、物事に対する視野が広まり、グループで1つのものを作り上げる大変さや楽しさを感じました。また、自分の将来を考える良い機会になりました。最後に、今回お世話になった中村ブレイスの中村社長様、スタッフの先生、その他出会った皆さん2日間素敵な貴重な時間をありがとうございました。
文学部 心理・社会福祉学科
4年 奥本 美佳
「世の中には、いろんな人がいる」―― この一言に尽きます。2日間にわたるプログラムは、本当に大満足でした。今の自分・将来なりたい自分を探る契機となり、誰の真似をするでもなく、自分が思うようがままに生きてみようと思いました。
私のグループは、武庫川女子大学1名、大阪大学1名、大阪薬科大学1名、関西大学2名、TA2名という構成で、それぞれの専攻も心理学、外国語、薬学、物理学、機械工学、栄養学と様々でした。6分野の人間が集まり、「10年後の日本社会を想定し、新しい医療・福祉サービスを提案する」というテーマについて、どのような結論が得られるのか予想不可能でした。
文系の私にとって、薬学・機械工学は特に未知の分野だったため、疑問に思ったことは積極的に質問するよう心がけました。質問に対する彼らの回答内容がわかりやすかったのに加え、順序立てて自分の専門について話す姿勢に感心しました。やはり、自分は論理的に話すのは苦手だなと思っていた矢先、私がポツリと発したなにげない一言が契機となり、グループの議論が展開していく瞬間があり、上手くは話せなくても、グループワークにはこういう貢献の仕方もあるのだなと思いました。これがまさに、1日目に中村社長が講演会の中でおっしゃっていた、「誰かのなにげない一言が、大きな力になる」ということなんだなと、一人実感していました。
2日目、発表日。どのグループも、さまざまな視点からテーマを捉えており、聞いているだけでも勉強になりました。それに加えて、発表中の声の出し方、表情、身振り手振り。これもかなり参考になりました。グループ発表ではもちろんのこと、グループワーク自己評価のまとめでの発表でも、それは大いに活かせたと思います。サマースクール終了後に、「発表の仕方、すごいよかったです!」と何人にも声をかけていただき、大きな自信になりました。
そして、気になるグループワーク結果発表!私たちは、2位の評価をいただきました。どんなときも相手の話を最後まで聞き、その人のことを尊重する姿勢を大切にしてグループワークを進めていったため、良いパワーポイントが仕上がったのだと思います。誰もが話せる、開かれた環境づくり――うなずきや笑顔、人の意見を聞くときはペンの動きを止めるといった何気ない心づかいは、社会に出て人と何かをやっていくにあたり重要なものだと改めて感じました。この2日間で得た多くのことを、今後の活動に生かしていきたいと思います。