
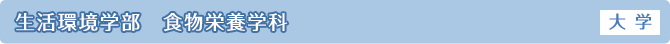
※学生向けに公開した内容からの抜粋です。文中の「皆さん」は、学生のことを指しています。
①教員についての評価に関する調査結果について
○教育や指導に熱意をもっている教員が多い
【認識】
- 個々の教員が教育や指導に十分な熱意を持ってあたっていることを示すものといえます。
【改善・改革の取り組み】
- さらに授業での講話力アップや授業展開の改善が図れるよう、学科FD委員会を中心として教員の資質向上をめざす取り組みを充実させていきます。
○授業中、学生の質問や意見に適切に対応してくれる教員が多い
【認識】
- 専門科目の授業が知識教授型で一方向的であるにもかかわらず、教員は学生の皆さんの質問や意見に適切に対応していると考えられます。
【改善・改革の取り組み】
- 学生の皆さんからの質問や意見に対する教員の対応については、学科FDの活動のなかで向上を図っていきます。
○授業の進め方や指導法をよく工夫している教員が多い
【認識】
- 自然科学の基礎知識を必要とする専門科目の授業において、理解が難しいと感じており、そのことが教員に対する指導法の工夫への低い評価に繋がっていると考えられます。
【改善・改革の取り組み】
- 教員レベルでの公開授業を利用した聴講や推奨授業モデルで授業指導法を学ぶなどの対策を講じます。
- 入試科目の改革、さらなるリメディアル教育の充実について検討していきます。
○勉学意欲をもたせてくれる教員が多い
【認識】
- 教員と学生の皆さんがともに管理栄養士を目指すという資格目標型の教育体制が反映されているためと思われます。
【改善・改革の取り組み】
- 学生の皆さんとともに、教員にも管理栄養士の具体的な活躍例(病院管理栄養士、保健所管理栄養士、栄養教諭、食品開発など)のデモの機会を増やし、双方のモチベーションを高めていく方策を取り入れていきます。
○授業以外でも教員とのコミュニケーションがとりやすい
【認識】
- 特に、4年生など高学年では全員が研究室のゼミ生として卒業研究にあたるため、教員とのコミュニケーションが十分とれていると認識しています。
【改善・改革の取り組み】
- 1年生などの低学年では、教員とのコミュニケーションがとりにくいことから、初期演習などを活用し、研究室訪問などの企画を通して教員と親しくなれる方策を取り入れていきます。
②大学での勉強(予習、復習、宿題等)時間についての調査結果について
【認識】
- 学習時間は、週当たり大学平均より1.5時間長いです。
- 実験・実習が多く、そのレポート提出に要する時間が長いためと考えられます。したがって、講義の予習、復習、宿題等に充てられる時間は、実際はさほど多くないものと思われ、学科の問題点であると言えます。また、レポート提出に追われ、講義の理解が不十分になっている可能性もあると推測できます。
【改善・改革の取り組み】
- 講義等における宿題の賦課などが、受動的学習態度の者には効果的方策と言えます。しかし、いたずらな課題の賦課はモチベーションを下げ、教員や教育に対する不満度を高めることにつながると思われます。如何に勉学に対するモチベーションを高め、能動的学生に育てるかについては、地道な方策を積み上げていくことに尽きると思われます。
- 勉学に対するモチベーションを高め、能動的学生を育てるために、管理栄養士の具体的な業務例(病院管理栄養士、保健所管理栄養士、栄養教諭、食品開発など)のデモの機会や卒業生との交流を増やすなどの方策を取ります。
③学科独自で行っている改善・改革のテーマとその取り組み
【テーマ】
「地域連携による実践活動の導入」
【改善・改革の取り組み】
- 地域との連携による実践活動の導入が勉学に対するモチベーションを高めると思われ、このようなプログラムを、現在の過密なカリキュラム体制にどう組み込んでいくかが課題と考えています。
▲ページトップへ

